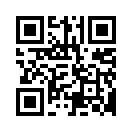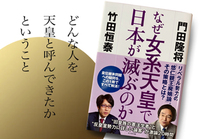2018年02月05日
この風景不思議に思ったことないですか?

って、
みんなが不思議に思うから 『 橋杭岩 』 は名勝なんだろうけど!
私が以前から不思議に思っているのは、
手前のゴロゴロしている岩です。
『 橋杭岩 』 の荒々しい感じと、
手前のゴロゴロしている岩の呑気な感じがとても対照的で
不思議に思っていたんですね。
県立紀伊風土記の丘 学芸員の
瀬谷今日子さんの 『 地震と考古学 』 というお話を聴きました。

このゴロゴロしているのは、
元は 『 橋杭岩 』 の一部だったのが崩落して、
津波で今の位置に運ばれたのだそうです。
だから一方向に偏って分布しているのだとか。
レーザー光線 ( て言ったかな? ) で正確に測っても
台風程度の大波では全く位置が変わっていないそうです。
“ 地震考古学 ” という学問があるのだそうですが、
なかなか面白いお話です。
考古学の分野で地震を見ることで、
解ることの例を興味深く沢山伺いましたが、
その中で、考えさせられたお話を1つ。
大阪で発見された弥生時代の大きな集落の遺構で、
集落があった間に何度も地震にあっていることが
地崩れの跡から解るけど、
地崩れの場所に建物が建っていた形跡が1つもないのだとか。
「 昔から人が住んでいた場所は、安全なところ 」
って、よく言われることですが、
まだ文字も持たない古い時代の人に
すでに安全に住む知恵があったんですね。
これだけ文明が進んだ時代の人がその知恵をなくしていることが
フ ・ シ ・ ギ !
Posted by CAOS at 01:49│Comments(0)
│日記