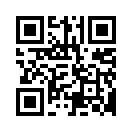2017年04月29日
今が “ その時 ” だったりして・・・


どこだか解りにくいからか、
この方向の写真はあまり使われないみたいですけど、
この角度の奈良ホテルも好きです。
『 一九四一年十月十日、奈良ホテルにて 』
で始まるエッセイです。

以前は、奈良って和歌山と同じくらい田舎だと思っていて、
比較にならないくらい都会だと認められるようになるのに
随分時間がかかりました。
イメージ通りの奈良。
田んぼや、すすきの野原みたいな広いところに、
古いお寺や集落がぽつんとある風景が
( 夕景で、建物はシルエットだったりします。 )
まだこのエッセイの時代には残っていて、
自然に自分がその風景に入り込めるんですね。
読みやすい文章ではないけど、写真集みたいな後口なのが不思議。
にしても、
最初の日付が、和暦では昭和16年10月10日、
最後に出てくるのが、同じ年の12月4日。
真珠湾を攻めて大きな戦争に突入する4日前なんですね。
もっと言うと、1週間後にはマレーシア沖で、
イギリスの軍艦2隻沈めてる!
「 ホテルでダラダラ時間を過ごした。」
とか、
とりあえず「 寺をまわった。 」とか「 散歩した。 」
とか、
「 浄瑠璃寺の女の子と柿をもぐ話をした。 」
とか、のんきなんですね。
世の中がとんでもないことに向かっていても、
日々の暮らしは、そんなものなのかも知れません。
2017年04月25日
ボクは信じる
専門家は、
専門家なために視野が狭かったり、
信じていることの他に興味を持たなかったりして、
自己矛盾から抜け出せなくなってるんじゃないかと
感じることがあります。
逆に、門外漢の説の方が無理がなく
説得力があったりするんですね。
地学や火山の専門家ではない人が、
古事記のエピソードを火山との関係で説明してしまっています。
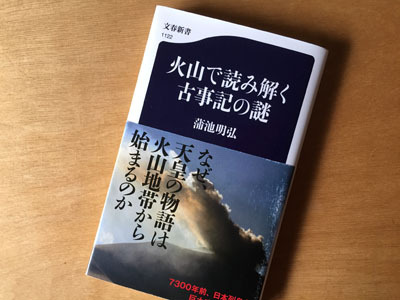
説得力がありました。
「 聖地は眠くなる 」の植島哲司氏の本を引用して、
最近発見された千五百万年前の紀伊半島の巨大カルデラと、
神武が熊野から奈良盆地を目指したルートとの関係を
説明しているのも面白い!

専門家なために視野が狭かったり、
信じていることの他に興味を持たなかったりして、
自己矛盾から抜け出せなくなってるんじゃないかと
感じることがあります。
逆に、門外漢の説の方が無理がなく
説得力があったりするんですね。
地学や火山の専門家ではない人が、
古事記のエピソードを火山との関係で説明してしまっています。
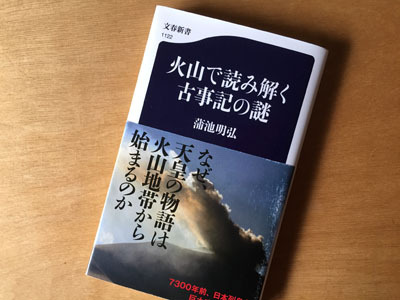
説得力がありました。
「 聖地は眠くなる 」の植島哲司氏の本を引用して、
最近発見された千五百万年前の紀伊半島の巨大カルデラと、
神武が熊野から奈良盆地を目指したルートとの関係を
説明しているのも面白い!

2017年04月21日
もう言わない・言わせない!
写真が上手く撮れないことを
ブログでも、もう鬱陶しがられるくらい何度も書いたけど、
最近ちょっと勉強しました。
で、
CANONのオーナー用のサイトで、
こういうコンテストがあったんですね。

これの〈初心者さん限定部門〉に応募していました。
なにせ、真っ当に写真撮るようになったのは、
去年ミラーレス一眼を買ってからで、
応募は初めてなので。

今日発表があって、
特賞4作品の中に入っていました。

(4番目に紹介されているのがちょっと気になるけど・・・)
なんか、とても嬉しい!
もう
写真ヘタとは言わない!
言わせない!
ブログでも、もう鬱陶しがられるくらい何度も書いたけど、
最近ちょっと勉強しました。
で、
CANONのオーナー用のサイトで、
こういうコンテストがあったんですね。

これの〈初心者さん限定部門〉に応募していました。
なにせ、真っ当に写真撮るようになったのは、
去年ミラーレス一眼を買ってからで、
応募は初めてなので。

今日発表があって、
特賞4作品の中に入っていました。

(4番目に紹介されているのがちょっと気になるけど・・・)
なんか、とても嬉しい!
もう
写真ヘタとは言わない!
言わせない!
2017年04月18日
単体で考えずに
こんなんつけてもらったら、
お行儀よくしていないといけない気がして疲れました。

建築家協会京都地域会の年次総会後の
記念講演と懇親会に
和歌山地域会会長さまの名代で出席しました。
先週土曜日のことですけど。
建築家協会会長の
『 京都・東京、建築・都市万華鏡 』
というタイトルの講演会でした。
六本木ヒルズや
新宿アイランド( LOVEのオブジェで有名なところですね )などの
大きなプロジェクトで、
“ 地域をつくってしまう ” ような大きな話でしたが、
小さなプロジェクトでも基本は同じなんだろうと思います。
地域が美しくなれば、暮らしが豊かになる。
資産価値も上がる。
治安も良くなる。
色々良くなる。
みんなが地域を意識して建物をつくれば、
みんながとても良くなると思っています。
お行儀よくしていないといけない気がして疲れました。

建築家協会京都地域会の年次総会後の
記念講演と懇親会に
和歌山地域会会長さまの名代で出席しました。
先週土曜日のことですけど。
建築家協会会長の
『 京都・東京、建築・都市万華鏡 』
というタイトルの講演会でした。
六本木ヒルズや
新宿アイランド( LOVEのオブジェで有名なところですね )などの
大きなプロジェクトで、
“ 地域をつくってしまう ” ような大きな話でしたが、
小さなプロジェクトでも基本は同じなんだろうと思います。
地域が美しくなれば、暮らしが豊かになる。
資産価値も上がる。
治安も良くなる。
色々良くなる。
みんなが地域を意識して建物をつくれば、
みんながとても良くなると思っています。
2017年04月13日
2度見れば、2通りの印象
この家の永い歴史の中では、
“ 1つの出来事 ” みたいな感じでしかなかったかも知れませんが、
映画の舞台に使われたことは
大変な出来事だろうと私は思います。

今月の『 豆の会 』、
先日挨拶にうかがった、耕心院さん
旧津田家を見学させていただきました。

参加のメンバーも感じていたのは、
この建物の保存と活用のことです。
なにせ広い敷地、大きな建物群なので難しい問題です。
前回から、季節が少し進んだだけだと思うけど、
庭の印象が随分違いました。

面白いものですね。
こんな立派なお庭でなくても、
季節の変化を楽しめることが庭の大事な役割だろうと思います。
こんな全体が真っ赤に見える花の咲き方をする木を
私はあまり知りません。

“ 1つの出来事 ” みたいな感じでしかなかったかも知れませんが、
映画の舞台に使われたことは
大変な出来事だろうと私は思います。

今月の『 豆の会 』、
先日挨拶にうかがった、耕心院さん
旧津田家を見学させていただきました。

参加のメンバーも感じていたのは、
この建物の保存と活用のことです。
なにせ広い敷地、大きな建物群なので難しい問題です。
前回から、季節が少し進んだだけだと思うけど、
庭の印象が随分違いました。

面白いものですね。
こんな立派なお庭でなくても、
季節の変化を楽しめることが庭の大事な役割だろうと思います。
こんな全体が真っ赤に見える花の咲き方をする木を
私はあまり知りません。

2017年04月07日
知らなかった訳ではないのに
江戸時代の女流絵師、葛飾応為。
北斎の娘ですが、
この人が描いた『 吉原格子先之図 』というのがあります。

何年か前にも話題になった時期がありましたが、
最近またちゃくちょくテレビで話題にされています。
専門家ではないので、間違っているかも知れませんが、
私の感覚では、江戸時代の人で、これだけ
“ 灯り ” と “ 影 ” を表現して描かれていることが驚きです。
西洋の絵画では、
ずっとずっと古くから当たり前に表現されていますけど、
日本ではちょっと違っていたように思います。
絵画の世界では珍しいけど、
生活の中ではこの時代に、見せたい部分を明るくして、
見なくて良いところは、“ 深み ” や “ 奥行き ” として、
空間を考えていたことが解ります。
この時代の人が知っていて、
今の日本人が忘れてしまっていることが不思議・・・。
クライアントとの打ち合わせで、
「 日本の明かりは、暴力的に明るすぎるよねぇ! 」
っていう話題で盛り上がったことで思い出したので、
ちょっと書いてみました。
北斎の娘ですが、
この人が描いた『 吉原格子先之図 』というのがあります。

何年か前にも話題になった時期がありましたが、
最近またちゃくちょくテレビで話題にされています。
専門家ではないので、間違っているかも知れませんが、
私の感覚では、江戸時代の人で、これだけ
“ 灯り ” と “ 影 ” を表現して描かれていることが驚きです。
西洋の絵画では、
ずっとずっと古くから当たり前に表現されていますけど、
日本ではちょっと違っていたように思います。
絵画の世界では珍しいけど、
生活の中ではこの時代に、見せたい部分を明るくして、
見なくて良いところは、“ 深み ” や “ 奥行き ” として、
空間を考えていたことが解ります。
この時代の人が知っていて、
今の日本人が忘れてしまっていることが不思議・・・。
クライアントとの打ち合わせで、
「 日本の明かりは、暴力的に明るすぎるよねぇ! 」
っていう話題で盛り上がったことで思い出したので、
ちょっと書いてみました。
2017年04月05日
ロマンチックな気もするけど・・・
紀伊半島の南端からモノを流したら、
黒潮に乗って東の方、なんなら北にふった方向に
流れていくだろうと思うのですが・・・。
まず南には向かいませんよね。
有名らしいですが、私は知りませんでした。

『 観音菩薩が住む
南方の浄土=補陀落世界 』
と信じて、
熊野那智の海岸から、棺のような船( ? )
で生きたまま海原に出る信仰があったのだそうです。
人が入ったら外から釘を打ち付けて出られなくしたり、
船底に穴を開けて栓をしておいて、
沖に出たら自分で抜いて沈む仕組みになったのがあったのだとか。
後には、広い地域に広まった信仰らしいので、
ある限定された場所で信じられていたことではないようですが、
現代の常識で理解するのは難しいですね。
著者が実験的に3隻の模型を那智湾から海に流してみたら、
1隻は、伊豆半島沖の新島、
1隻は、すぐ近くの古座川町に流れ着いたのだそうです。
残りの1隻が見つからなかったということで、
補陀落世界にたどり着いたのかもしれない。
と、あとがき には書かれていました。
黒潮に乗って東の方、なんなら北にふった方向に
流れていくだろうと思うのですが・・・。
まず南には向かいませんよね。
有名らしいですが、私は知りませんでした。

『 観音菩薩が住む
南方の浄土=補陀落世界 』
と信じて、
熊野那智の海岸から、棺のような船( ? )
で生きたまま海原に出る信仰があったのだそうです。
人が入ったら外から釘を打ち付けて出られなくしたり、
船底に穴を開けて栓をしておいて、
沖に出たら自分で抜いて沈む仕組みになったのがあったのだとか。
後には、広い地域に広まった信仰らしいので、
ある限定された場所で信じられていたことではないようですが、
現代の常識で理解するのは難しいですね。
著者が実験的に3隻の模型を那智湾から海に流してみたら、
1隻は、伊豆半島沖の新島、
1隻は、すぐ近くの古座川町に流れ着いたのだそうです。
残りの1隻が見つからなかったということで、
補陀落世界にたどり着いたのかもしれない。
と、あとがき には書かれていました。