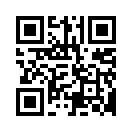2018年04月28日
シナ布
シナという木があります。
PCで変換出来ませんでしたが、漢字で木偏に品と書きます。
これを使った合板は、
木肌に癖がなくて美しいのと値段が安いこともあって
建築でも比較的使いやすい材料です。
キルト作家の黒田街子さんが
古代からあった布で作られているとして
持たれていたコースター

シナの樹皮を縦横の糸にして織っています。

黒田さんのお話しでは、
何年使ってもヘタらないのだとか。
シナ合板と同じ香りがして
とても興味深いものでした。
今月の 『 茅の会 』 は、
黒田さんのキルト教室の和歌山の生徒さん達の
意見発表を聞かせてもらいましたが、
絵の具を使う絵画などと違って、
キルトは、必要な色 ( 柄 ) の布を持っていなければ
イメージ通りの表現ができない。
以前から聞いていた話ですが、
私には、このことがとても気になることでした。
キルトは、自由な表現のために
“ 布集め ” するのも楽しそうなのだけど、
建築で、建材の色番に支配されるのはつまらない。
この違いは何なんだろう?
建材でもタイルなんかだとつまらなくないから、
世の中に沢山ある中から選べるかどうか。
・ ・ ・ なんだろうか?
結論の部分で随分迷走してしまいました。
PCで変換出来ませんでしたが、漢字で木偏に品と書きます。
これを使った合板は、
木肌に癖がなくて美しいのと値段が安いこともあって
建築でも比較的使いやすい材料です。
キルト作家の黒田街子さんが
古代からあった布で作られているとして
持たれていたコースター

シナの樹皮を縦横の糸にして織っています。

黒田さんのお話しでは、
何年使ってもヘタらないのだとか。
シナ合板と同じ香りがして
とても興味深いものでした。
今月の 『 茅の会 』 は、
黒田さんのキルト教室の和歌山の生徒さん達の
意見発表を聞かせてもらいましたが、
絵の具を使う絵画などと違って、
キルトは、必要な色 ( 柄 ) の布を持っていなければ
イメージ通りの表現ができない。
以前から聞いていた話ですが、
私には、このことがとても気になることでした。
キルトは、自由な表現のために
“ 布集め ” するのも楽しそうなのだけど、
建築で、建材の色番に支配されるのはつまらない。
この違いは何なんだろう?
建材でもタイルなんかだとつまらなくないから、
世の中に沢山ある中から選べるかどうか。
・ ・ ・ なんだろうか?
結論の部分で随分迷走してしまいました。
2018年04月26日
いい場所
自分の知っていることが
世の中の標準だと思いこんでしまうこと
って多いみたいで、私にも同じことがあるみたいです。
須佐神社には桃の印が付いたものが沢山あるので、
神社っていうのはそういうものだと思っていましたが、
桃は須佐神社の神紋なので使われているけど、
神社の紋としては全国でも2~3の例があるだけで
とても珍しいのだとか。
そう聞いていると、
確かに他の神社では見たことがない気がします。
今月の 『 豆の会 』 は、
須佐神社に遠征して、
禰宜さんから神社の説明をお聞きしたあと
元々須佐神社があったとされる山の上
“ 元宮 ” まで歩きました。

現代の神社もけっこう階段を上がりますが、
さらに山道を片道20分ほどの工程です。
私は2度目ですが、不思議な場所です。
“ 聖地 ” の空気なんですね。
以前にも書いたけど、
「 聖地は移動しない 」
祈りの場所は、そのときにヒトの都合で移動することがあるけど、
本来の “ 聖地 ” は移動しない。
そんなことを実感します。
世の中の標準だと思いこんでしまうこと
って多いみたいで、私にも同じことがあるみたいです。
須佐神社には桃の印が付いたものが沢山あるので、
神社っていうのはそういうものだと思っていましたが、
桃は須佐神社の神紋なので使われているけど、
神社の紋としては全国でも2~3の例があるだけで
とても珍しいのだとか。
そう聞いていると、
確かに他の神社では見たことがない気がします。
今月の 『 豆の会 』 は、
須佐神社に遠征して、
禰宜さんから神社の説明をお聞きしたあと
元々須佐神社があったとされる山の上
“ 元宮 ” まで歩きました。

現代の神社もけっこう階段を上がりますが、
さらに山道を片道20分ほどの工程です。
私は2度目ですが、不思議な場所です。
“ 聖地 ” の空気なんですね。
以前にも書いたけど、
「 聖地は移動しない 」
祈りの場所は、そのときにヒトの都合で移動することがあるけど、
本来の “ 聖地 ” は移動しない。
そんなことを実感します。
2018年04月22日
所変われば 道端編
台南市の道端でも何だか面白いモノを見付けて!
みょうに可愛い道路標示

直角に交わる交差点なんだけど、
何だか樹木のトレードマークみたい。
バイク専用車線 ( だと思う )

バイク用車線があるから、
「 バイクはここを走ってくる 」 なんてことを思っていると
無傷では日本に帰れない!
すいていれば歩道だって走る!
当然車道も走る!
番外編みたいな感じ

この乗り物はこれだけでもステキなんだけど、
前輪タイヤに注目!

脚力が必要ですナ!
台湾の道路では、クルマもバイクも ( よく解らない乗り物も )
みんな好き勝手に暴走しているように見えるけど、
リンさんの運転を見ていて感じました。
きっと外国人には解らない
現地の人達だけが解る法則があって、
それにしたがって走っている。
・ ・ ・ はずだ!
そうでないと
もっといっぱい交通事故が起きると思うなぁ ・ ・ ・ 。
みょうに可愛い道路標示

直角に交わる交差点なんだけど、
何だか樹木のトレードマークみたい。
バイク専用車線 ( だと思う )

バイク用車線があるから、
「 バイクはここを走ってくる 」 なんてことを思っていると
無傷では日本に帰れない!
すいていれば歩道だって走る!
当然車道も走る!
番外編みたいな感じ

この乗り物はこれだけでもステキなんだけど、
前輪タイヤに注目!

脚力が必要ですナ!
台湾の道路では、クルマもバイクも ( よく解らない乗り物も )
みんな好き勝手に暴走しているように見えるけど、
リンさんの運転を見ていて感じました。
きっと外国人には解らない
現地の人達だけが解る法則があって、
それにしたがって走っている。
・ ・ ・ はずだ!
そうでないと
もっといっぱい交通事故が起きると思うなぁ ・ ・ ・ 。
2018年04月21日
所変われば
国が違えば少しずつカタチが違うモノがあるみたいで、
台南市のホテルで見付けたコンセントが
なんだか面白かったのでご紹介。
歯磨きしながら気付いた
洗面台前のウインクするコンセント。

テーブルの前に付いていた
オッサン顔のコンセント。

ベッドサイド
左がブタ鼻・真ん中がビックリしているコンセント。

真ん中のは右目と左目の大きさが違って、
なかなか芸が細かい!
因みに、
日本で普通に見る形の100Vのコンセント。
台湾では110Vですが、
iPhoneもカメラのバッテリーも普通に充電できました。
カメラのバッテリーを充電して出掛けている間に
掃除の人が入って抜かれていたのには慌てたけど ・ ・ ・ 。
台南市のホテルで見付けたコンセントが
なんだか面白かったのでご紹介。
歯磨きしながら気付いた
洗面台前のウインクするコンセント。

テーブルの前に付いていた
オッサン顔のコンセント。

ベッドサイド
左がブタ鼻・真ん中がビックリしているコンセント。

真ん中のは右目と左目の大きさが違って、
なかなか芸が細かい!
因みに、
日本で普通に見る形の100Vのコンセント。
台湾では110Vですが、
iPhoneもカメラのバッテリーも普通に充電できました。
カメラのバッテリーを充電して出掛けている間に
掃除の人が入って抜かれていたのには慌てたけど ・ ・ ・ 。
2018年04月20日
異文化交流 後編
台湾旅行2日目。
前日知り合った現地人の黄さんから
八田與一の銅像があるところまで案内する。
と誘われて、
1人単独行動して待ち合わせの14時まで街を散策たあと
ホテルのロビーで黄さんと再開。
黄さんの奥さんリンさんの ( レーシングドライバーみたいな ) 運転で


烏山頭ダムに向かいました。
台南市から高速道路で1時間足らずの距離だったかな?
自分で行くにはなかなか大変そうな場所です。
写真では何度も ・ 何度も見た八田與一。

感動しました。
戦前に作られたこの銅像を守り抜いたのは台湾の人達です。
それだけ愛されて、
現代も続く台湾人の日本贔屓はこの人がつくった。
ここに来られたことは感動です。

八田與一が現地の人と力を合せて造った烏山頭ダム。
「 今でもビクともしない丈夫なダム 」
と、台湾人の黄さんが日本人の私に自慢する。
とても嬉しかったです。

そして、八田與一の業績を伝える記念館もあります。

日本にも色々な所にこんな感じの記念館があるけど、
上映されるビデオを真剣に観ている人がいないでしょう?
ここでは日本人の業績の紹介を大勢の台湾人が
最後まで真剣に観ているんです。
とても誇らしく思いました。
( どこぞの半島で、ウソの歴史を教育するのとは大違い! )
中華系の人は何かを表現するのに謙遜しない。
「 帰りは、
台湾で1番美味し良いマンゴーかき氷の店に連れて行きます 」
と言われて
「 マンゴー嫌いなんです 」
と言えないシャイな日本人は素直に着いていく。

中華系の人は歓迎の仕方が大胆!
3人で4人前注文して、黄さんとリンさんが少しずつ取って、
「 あとは上野山さんがたっぷりどうぞ! 」
って、
「 マンゴー嫌いなんです。 」
って言えなかったから ・ ・ ・ 。
台南市内に戻って、さらに夕食ごちそうになって
夜の街を案内してもらっていたら
お腹痛くなって、黄さんにトイレ探してもらって
など、色々ありまして、
ホテルの部屋に戻ったのは何時だっただろう?
なにせ2万歩近く歩いて

『 課長島耕作 』 を読んで日本語を覚えたという
黄さんの日本語もコミュニュケーションが簡単ではないので
とても疲れて寝ていました。
「 何の音だろう? 」
聞き慣れない電子音。
ホテルの部屋の電話で起こされました。
午前1時前。
「 飲んでるから608号室においで 」
“ おいで! ” だったか “ 来い! ” だったか定かでないけど。
結局飲み直し。
一緒に行った有田設計事務所協会のメンバー。

ってなことで、
朝ゆっくりな出発だったけど起きられなくて、
3日目は移動だけの日になりました。
往路と同じルートを逆にたどるだけ。

現地の人とも沢山の時間を過ごしてとても良い旅でした。
帰りの飛行機から見た台南の平地。( 多分 )

この広い土地を八田與一の烏山頭ダムが潤した。
改めて感動しました。
思い返してみれば、
台湾にいる間に私が自分でお金を出したのは
2日目の午前中に買ったペプシの代金だけ。
100円もしていない。
旅費も会の貯金から半額補助が出ているのでとても安くて、
そうなると、行きの関空で没収された
ヘアムースとアフターシェーブローションを
帰国後買い直したのがイタイ!
旅行費用の10%くらいの計算になる ・ ・ ・ 。
前日知り合った現地人の黄さんから
八田與一の銅像があるところまで案内する。
と誘われて、
1人単独行動して待ち合わせの14時まで街を散策たあと
ホテルのロビーで黄さんと再開。
黄さんの奥さんリンさんの ( レーシングドライバーみたいな ) 運転で


烏山頭ダムに向かいました。
台南市から高速道路で1時間足らずの距離だったかな?
自分で行くにはなかなか大変そうな場所です。
写真では何度も ・ 何度も見た八田與一。

感動しました。
戦前に作られたこの銅像を守り抜いたのは台湾の人達です。
それだけ愛されて、
現代も続く台湾人の日本贔屓はこの人がつくった。
ここに来られたことは感動です。

八田與一が現地の人と力を合せて造った烏山頭ダム。
「 今でもビクともしない丈夫なダム 」
と、台湾人の黄さんが日本人の私に自慢する。
とても嬉しかったです。

そして、八田與一の業績を伝える記念館もあります。

日本にも色々な所にこんな感じの記念館があるけど、
上映されるビデオを真剣に観ている人がいないでしょう?
ここでは日本人の業績の紹介を大勢の台湾人が
最後まで真剣に観ているんです。
とても誇らしく思いました。
( どこぞの半島で、ウソの歴史を教育するのとは大違い! )
中華系の人は何かを表現するのに謙遜しない。
「 帰りは、
台湾で1番美味し良いマンゴーかき氷の店に連れて行きます 」
と言われて
「 マンゴー嫌いなんです 」
と言えないシャイな日本人は素直に着いていく。

中華系の人は歓迎の仕方が大胆!
3人で4人前注文して、黄さんとリンさんが少しずつ取って、
「 あとは上野山さんがたっぷりどうぞ! 」
って、
「 マンゴー嫌いなんです。 」
って言えなかったから ・ ・ ・ 。
台南市内に戻って、さらに夕食ごちそうになって
夜の街を案内してもらっていたら
お腹痛くなって、黄さんにトイレ探してもらって
など、色々ありまして、
ホテルの部屋に戻ったのは何時だっただろう?
なにせ2万歩近く歩いて

『 課長島耕作 』 を読んで日本語を覚えたという
黄さんの日本語もコミュニュケーションが簡単ではないので
とても疲れて寝ていました。
「 何の音だろう? 」
聞き慣れない電子音。
ホテルの部屋の電話で起こされました。
午前1時前。
「 飲んでるから608号室においで 」
“ おいで! ” だったか “ 来い! ” だったか定かでないけど。
結局飲み直し。
一緒に行った有田設計事務所協会のメンバー。

ってなことで、
朝ゆっくりな出発だったけど起きられなくて、
3日目は移動だけの日になりました。
往路と同じルートを逆にたどるだけ。

現地の人とも沢山の時間を過ごしてとても良い旅でした。
帰りの飛行機から見た台南の平地。( 多分 )

この広い土地を八田與一の烏山頭ダムが潤した。
改めて感動しました。
思い返してみれば、
台湾にいる間に私が自分でお金を出したのは
2日目の午前中に買ったペプシの代金だけ。
100円もしていない。
旅費も会の貯金から半額補助が出ているのでとても安くて、
そうなると、行きの関空で没収された
ヘアムースとアフターシェーブローションを
帰国後買い直したのがイタイ!
旅行費用の10%くらいの計算になる ・ ・ ・ 。
2018年04月18日
異文化交流 前編
新しく買ったヘアムースとアフターシェーブローション

飛行機の手荷物不可とは知っていながら、
何とかなりそうな気がして持っていったけど、
結局、関空で取り上げられたので ・ ・ ・ 。
っていうようなことから始まった台湾旅行。
降り立った高雄空港は “ 夏 ” でした。

在来線特急で台南市へ

その日の内に、
林百貨店

日本が統治した時代に、日本人の林さんが建てたものだそうです。
内部も時代がかって良い感じ。

孔子廟

こんな感じは日本で見たら嫌いだけど、
見る場所が違うと有な感じがするから不思議。

お茶でも飲もうと有名 ( らしい ) お店へ。
誰がこんな横向かないと入れないような
狭い路地の奥にお店があると思う?


まぁ中はちゃんとしているのだけど!

ってなことで、この日の主な観光は終わって、
お宿は、ちょっと良いホテルなんだけど、
相場が安いから日本人的にはとてもリーズナブル。

部屋から見た台南市内の夜景

晩御飯はちょっと豪華に中華三昧。

写真はフカヒレだぜぃ!
で、2日目が少々ハプニングで、
予定では他のメンバーと一緒に
日本人建築家が最近建てたオペラハウスを見に行く予定でしたが、
前日に知り合った現地人の黄さん夫妻と話したときに
八田與一の話をしたら
「 明日八田與一の銅像があるところに連れて行ってあげる。 」
ということになって、 勝手に単独行動。
ホテルに迎えに来てくれるのが14時ということで
それまで1人で街を歩く歩く!
赤カン樓は有名な観光地だそうです。


観光地よりも普通の町中が面白い。

これなんか美しいと思ったなぁ。

そして、今回の旅で知ったこと。
躊躇なく水が飲めて、
道を歩いてもクルマやバイクが突っ込んで来ることがなくて
頭の上を絶え間なく軍用機が飛ぶこともない


そんなことを当たり前だと思っているのは
日本人の幻想だ!
ちょうど旅程の半分なので、
長くなるし一旦ここまでにします。

飛行機の手荷物不可とは知っていながら、
何とかなりそうな気がして持っていったけど、
結局、関空で取り上げられたので ・ ・ ・ 。
っていうようなことから始まった台湾旅行。
降り立った高雄空港は “ 夏 ” でした。

在来線特急で台南市へ

その日の内に、
林百貨店

日本が統治した時代に、日本人の林さんが建てたものだそうです。
内部も時代がかって良い感じ。

孔子廟

こんな感じは日本で見たら嫌いだけど、
見る場所が違うと有な感じがするから不思議。

お茶でも飲もうと有名 ( らしい ) お店へ。
誰がこんな横向かないと入れないような
狭い路地の奥にお店があると思う?


まぁ中はちゃんとしているのだけど!

ってなことで、この日の主な観光は終わって、
お宿は、ちょっと良いホテルなんだけど、
相場が安いから日本人的にはとてもリーズナブル。

部屋から見た台南市内の夜景

晩御飯はちょっと豪華に中華三昧。

写真はフカヒレだぜぃ!
で、2日目が少々ハプニングで、
予定では他のメンバーと一緒に
日本人建築家が最近建てたオペラハウスを見に行く予定でしたが、
前日に知り合った現地人の黄さん夫妻と話したときに
八田與一の話をしたら
「 明日八田與一の銅像があるところに連れて行ってあげる。 」
ということになって、 勝手に単独行動。
ホテルに迎えに来てくれるのが14時ということで
それまで1人で街を歩く歩く!
赤カン樓は有名な観光地だそうです。


観光地よりも普通の町中が面白い。

これなんか美しいと思ったなぁ。

そして、今回の旅で知ったこと。
躊躇なく水が飲めて、
道を歩いてもクルマやバイクが突っ込んで来ることがなくて
頭の上を絶え間なく軍用機が飛ぶこともない


そんなことを当たり前だと思っているのは
日本人の幻想だ!
ちょうど旅程の半分なので、
長くなるし一旦ここまでにします。
2018年04月01日
“ 意味 ” をさぐる
花も盛りで

って、ホントはピーク過ぎてる感じだったけど、
小川には、わさびも育つ
紀美野町・蒲公英工房の春。

黒田街子さんのキルト教室の作品展と同時開催の 『 茅の会 』 。
今月は、佐藤溯芳さんの 『 日本書紀 』 のお話しでした。
古事記でも日本書紀でも、
頻繁に場面の設定や目線がズレる感じがして、
「 まだ文学のテクニックが稚拙で、下手だったんだろう。 」
と思っていましたが、
研究者は、
「 この場面の展開、目線にはどんな意味があるんだろう。 」
と考えるらしいです。
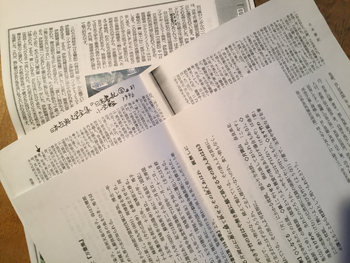
そんな風に聞くと、
「 何か意味があるんだろう。 」 と思えてきます。
単純なものですが、
誰も答えが解らないことなので、イメージすることが大切。
人の話を聞かないと考えの幅はなかなか広がりません。

って、ホントはピーク過ぎてる感じだったけど、
小川には、わさびも育つ
紀美野町・蒲公英工房の春。

黒田街子さんのキルト教室の作品展と同時開催の 『 茅の会 』 。
今月は、佐藤溯芳さんの 『 日本書紀 』 のお話しでした。
古事記でも日本書紀でも、
頻繁に場面の設定や目線がズレる感じがして、
「 まだ文学のテクニックが稚拙で、下手だったんだろう。 」
と思っていましたが、
研究者は、
「 この場面の展開、目線にはどんな意味があるんだろう。 」
と考えるらしいです。
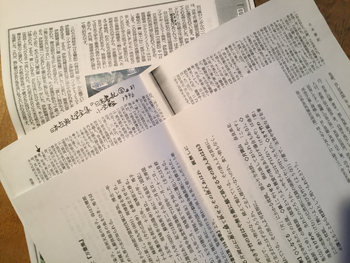
そんな風に聞くと、
「 何か意味があるんだろう。 」 と思えてきます。
単純なものですが、
誰も答えが解らないことなので、イメージすることが大切。
人の話を聞かないと考えの幅はなかなか広がりません。