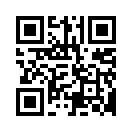2014年04月30日
『 芙蓉の人 』
“ 最初にした人 ” がいるんですよね。
富士山頂に初めて観測所を建てた人もいる。
普通は、国の力で建てたんだろうと思うけど、
ひとりの情熱を持った男が私費で建てたことを
最近知りました。

情熱を持って建てたのは “ 男 ” だったけど、
本当の業績は、その妻だったことが
凄くて、面白い。
夫婦が文字通り命を賭して成し遂げようとした仕事。
犠牲にしたものの大きさ。
巻末の 『 解説 』 に
「 情熱と気概と勇気と忍耐 」 とを持った女性
と書かれていますが、
明治の女の強さに感激しました。
今、国語辞典をひくと
『 芙蓉 』 は、
①ハスの漢名
②夏秋ころ、薄い・紅色で大型の花を開く落葉低木
[ ―峰 ] 「 富士山 」 の異名
だそうです。
初めて知った ・ ・ ・ 。
なんとなくですけど、
キレイな感じがする言葉ですね。
2014年04月29日
私の 『 伊勢物語 』
年に1度、
恒例になった 『 茅の会 』 の修学旅行。
私のメインは 『 潮騒 』 の舞台、神島でしたが、
他にも見どころ盛りだくさんでした。
最初に立ち寄った松阪。
始めて知りましたが、
紀州藩の領地だったそうです。
逃したくなかったのが、
『 小津安二郎青春館 』

小さな施設ですが、
たっぷり時間を使って楽しみました。
( そのためにお昼ご飯、予約していた時間より随分遅れて、
「 あとの予約が入っているのでお早くお願いします。 」
とか言われてしまったけど ・ ・・ 。)
小津安二郎は、青春時代の10年間を松阪で過ごしたそうで、
「 小津映画の低いカメラ位置は、
松阪の草むらに寝転んでみた風景の印象が原点。 」
と説明されたけど、
本当かどうか、私には解りません。
こんな家並みも残っていて、
いい感じでした。

街の一部が残っている感じなのはどこでも同じですが、
豊かな家が多かったんだなという印象。
この路地好きです。

松阪城跡からみた 『 御城番屋敷 』 。

家並みは、
隣と違うことを誇るよりも、
お互いが周囲のことを思い遣りながら
調子を合わせることのほうがずっと価値があることを
思い知らされるんですよね。
こういう美しい風景を見ると。
初日は、
このあと 『 斎宮歴史博物館 』 によりました。
建物に趣がないことと、
『 斎王 』 は、天武天皇の時代、
奈良に都があったころから始まっているのに、
京都から伊勢に向かう道のりの大変さとか、
文化とかが中心に紹介されていたのが、
私の好みでは 残念!
お宿は、
私の希望で神島の民宿にしてもらったので、
鳥羽にクルマをおいて、船で45分。
困ったことに、
クルマを下りるときにカメラを忘れてしまいました。
民宿でデジカメをお借りして、
幸いなことにメンバーの佐藤さんがSDカードの予備を
持たれていたので、お借りしました。
( 2ギガ ・ 4ギガ ・ 8ギガがありますけど、
どれが必要ですか?
って、そんなに沢山持ち歩いている人と初めて会った! )
忘れてならない民宿での海の幸三昧。
有田で生活していると、お刺身 なんてモノは
特別なものとは思っていない傾向がありますが、
生きの良さと、翌朝に残しておいてもらっても
結局食べきれなかった量に驚き!
で、
翌日は、朝から島を1周して
『 潮騒 』 の舞台めぐり。
・ ・ ・ この部分だけを前回書きました。
午前中に船に乗って、本土に戻りました。
昨年 式年遷宮を終えた 『 伊勢神宮 』 。


内宮は2度目ですが、外宮は今回が初めてです。
ここで “ 国家の安泰 天下の泰平 ” を祈願して
今回の私の伊勢行を終えましたが、
私なりに、伊勢神宮について勉強していったのに、
一国民には本宮をみることが出来ないのが残念。
辛うじて、
内宮と外宮の
千木の先の形状の違いを確認できただけ ・ ・ ・ 。
だけど、
千木 ・ 鰹木があれだけ金ピカに輝いているのは
神々しさがあると言うことも出来るかも知れないけど、
私には不自然な印象だったナ ・ ・ ・ 。
みんなが行く観光地もいいんだけど、
一般的なツアーでは、
普通ちょっと行かないようなところをリクエストしても
受け入れられる 『 茅の会 』 恒例修学旅行。
今回は、私には神島がメインでしたが、
昨夜からもう一度三島由紀夫の 『 潮騒 』 を読み直しています。
前回読んだときとのリアリティの違いが面白い。
2014年04月28日
『 潮騒 』 の舞台を訪ねる
畑仕事していたおじいさんは、
「 三島先生が家の前を毎日行き来していたのを見たし、
映画化した女優さんを全員見た。 」
とのこと。
伊勢湾に浮かぶ周囲4㎞ほどの小さな島。
『 神島 』 は、
鳥羽の港から市営の連絡船で今でも40分ほどかかります。
三島由紀夫がこの島に注目しなかったら
今頃はどんな感じになっていたでしょう?
三島由紀夫の小説 『 潮騒 』 の舞台。
神島 を訪ねました。

今では、ケーブルテレビが観れるし、
本土から水道もひかれて、
以前ほどの
離島の不便さは無くなっているように見受けられました。

以前は、小さな島では水不足が慢性化していて、
この溝を流れる表層水で
島の女たちが洗濯していました。
小説でもここで一波乱あります。
八代神社のこの階段も重要な舞台。

都会に住んでいる灯台長の娘が帰って来て、
やきもちから主人公の2人の立場を悪くする展開は、
物語の構成ではとても大切な部分です。

何と言っても ・ ・ ・
なんっちゅうても ・ ・ ・
『 潮騒 』 で、1番大切な場所はここ!

監的哨です。
天候が荒れて、
漁が休みになったらここで会おうと2人が約束するんですね。

この四角い部分のたき火で、
吉永小百合さんが
のちには、山口百恵さんが、
濡れた服を脱いで乾かしていたら、
目を覚ました若者が 見せろ と言う。
「 その火を飛び越して来い。
その火を飛び越して来たら 」
っていうドキドキする場面覚えていませんか?
吉永小百合や山口百恵レベルと約束していたら、
ものすごくキツイ道なんだけど、
嵐の中でもムリして行く っちゅうネン!
グルっとまわって、
4㎞、2時間ほどの行程ですが、
上り下りの激しさが尋常ではなかったのですが、
なんでも行きたかった場所。
とても良い体験でした。
その他にも、
今回行きたかった場所があって、
実現したのだけれど、
ながくなるので日を改めます。
2014年04月25日
初めてのお泊り!
建築家協会奈良地域会の年次総会に出席しました。

正確には、
総会後の記念講演会と懇親会への出席。
伊勢神宮から直接仕事を依頼される唯一の左官、
木村和也氏と、
左官仕事の表現が多い空間美術家の
木村謙一氏の対談形式で、仕事を紹介するかたちでしたが、
非常に良い企画でした。

懇親会の席で、
お二人と沢山話しましたが、
日本を代表するレベルの人の仕事でも、
なかなか “ ホンモノ ” が理解されにくいようです。
『 古びの美学 』 みたいなところで
価値感を共有できたことが私には嬉しかったけど、
本当は、そんなことが共有できるのはおかしい!
と思い直してみたりして ・ ・ ・ 。
息子が受験のときに利用したホテルが、
安い割にはとても印象が良かった話を聞いていたので、
会場から近いこともあって、
今回私が利用しました。

値段が安い分だけ狭くて、居室部分2.5m×2.2m。
とても狭いけど、
( 懇親会で少しいただいたあと、部屋に荷物を置いて1人で外に出たので )
酔っ払って部屋に帰って1人寝るだけの目的に、
これ以上広さは必要もないだろうと思います。
目的と値段の安さが明確であれば、
全く問題のない面積!
というのが、私の感想です。
そう言えば、
息子のところに泊まる以外で、
奈良で泊まるのは初めてでした。
次は、奈良ホテルにしよう!
2014年04月21日
“ 常識 ” って正しいのか?
LED照明とか、
それが良い物と考えることが “ 常識 ” みたいになっているけど、
私は疑っています。
10年後か、20年後か、
時間が経てば、「 そんなのが良いと思っていたよねぇ 」
みたいな会話をしているかも知れない。
私が建築の仕事に着いてからでも
そんなことを沢山経験しています。
伊勢神宮は、
1300年の間、20年ごとに全く形を変えずに建て替えられてきた。
って、多くの人が常識だと思っているけど、
20年ごとには建て替えられていないし、
120年余りのあいだ中断されたこともあったし、
建物の形も、配置も違っている。
( むしろ、建て替えられるたびに変わってきた )

のだそうです。
誰かが言ったことが
広まって “ 常識 ” になるのだと思いますが、
言葉だけを信じて、誰も検証しなければ、
それが正しいかどうかなんて解らないということなのでしょう。
2014年04月17日
『 実物に触れる 』 ことは、どんなことでも感動的なので
とても良いタイミングで届きました。
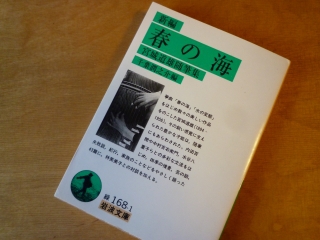
『 邦楽家族 』 辻本家のいつだったかの演奏会で、
奥様の啓子さんが話された
「 宮城道雄の春の海 云々 」 のお話が
何となく印象に残っていて
辻本ご夫妻にお願いした
今日の 『 豆の会 』 のプログラムをつくっているときに、
宮城道雄が音楽だけではなくて文才も優れた人で
随筆家としても有名なことを知ったので取り寄せてみました。
ガッコウでは教えてくれなかったけど
「 音楽って楽しい! 」

いつもの 『 豆の会 』 とは趣をかえて、
今月は湯浅町伝建地区内にある
太田久助吟製さんの 『 まえぐら 』 をお借りして、
尺八の辻本公平さん、お琴の啓子さんによる
邦楽演奏会でした。
本当に音楽を愛しておられるご夫妻ですから、
演奏は気持ち良く心に入ってきます。
楽器のことや、邦楽のお話もとても興味深くて、
良い時間をいただきました。
1つのことに触れると、
次に知りたいことが新しく生まれる。
『 豆の会 』 は、
そんな場であればいいなと思っています。
2014年04月09日
少し手間をかけて
父が靴の手入れを教える。
なぁんてことがカッコいいと思っていて、
去年の春に実行しました。
革は自然素材なので、
使い込むほどに味が出てきますよね。
合成皮革では、そんなわけにはいかない。
そこらへん、
自然素材の建築と、
新建材の建築との関係に似ているように思います。
私自身の靴は、
ローファーは、同じメーカーの同一品番を
何十年も履き続けているので、
注文だけして、宅配で配達されても問題ありません。

届いた靴に、
まず、下地作りのつもりで手入れしてから。
とか思ってクリームを塗っていたら、
自分の爪でキズつけてしまった ・ ・ ・ 。
何をしていることやら ・ ・ ・ 。
そのうちキズが気にならなくなるのも
自然素材の特徴だと思いますが!
2014年04月07日
筋が通っているから!
もちろん建築でも、
およそ芸術に分類される全部の分野で優れた作品には、
時間が経ってから、他人の手で
時代背景や、表現手法、作者の心理状態、
その効能など、分析する文章が書かれていますよね。
( 当たり前ですワナ!
優れていないモノを分析する物好きはない ・ ・ ・ )
“ 分析できる ” ということが大切で、
優れた作品は、しっかりとした筋が通っていて、
確かな考えがあって表現を膨らませているから
のちの人が分析できるのだろうと思うのです。
サラリーマンで管理職だったころ、
他人様が設計したのを
もっと良くなるように直すというようなことを
たびたび依頼されましたが、
私には、どこから手を付けて良いか解らなくて
出来ませんでした。
その頃は、元々設計した人と自分との間に
圧倒的な力の差がないからだと思っていましたが、
キチンとした文脈のような筋が通っていないモノに
どの部分を残して、
どの部分を変えるという判断のしようがない。
ということの方が大きかったのだろうと思います。
これも、優れた力を持った人の仕事を
のちに解析した本です。

小津安二郎の “ 美学 ” のようなものを
作品作りと合わせて解説していますが、
とても面白い!
優れた人は、
その生き方、物の選び方にも妥協がないのだけれど、
言葉も良いんですよね。
「 リンゴの絵をかいていて、
うまくいかないからといって、
柿や桃をかき始めるようじゃダメだよ。
うまくいってもいかなくても ・ ・ ・ 。
私はそういう人しか信用しない。 」
いつか、真似して使ってやろうと思っています。
2014年04月05日
“ 初心 ”
昨日は、1日仕事らしい仕事もせずに
あちこち走り回る1日で、
夜、建築士会の有田支部で年次総会前の理事会があって、
その後、お付き合いで少し飲んで、
日付が変わった頃に帰って来ましたが、
すぐに寝てしまったようです。
滅多にないことですが、
2時間ほどで目覚めてしまって、
あとがいけない ・ ・ ・ 。
眠れません。
PCを開いて、
古い資料を整理したりしていましたが、
そう言えば、
事務所を開いたばかりで全く仕事がなかった頃は、
こんな時間に、
今は無くなったOCNのサイトに延々書き込みをしていました。
「 建築ってこういうものじゃないか 」
「 家を建てる人は、こういう風に考えた方がいいんじゅないか 」
というようなことが多かったのですが、
その内、事務所としての実績が全くない私に
「 あなたの意見が面白いから 」
という ( だけの ) 理由で、
遠方の人から依頼をもらったりするようになりました。
10年以上の時間が経って、
基本的な考えも、姿勢も変えていないと思っていますが、
あの頃とは、
気持ちの発信の仕方が変わってしまったなぁ。
と、
とても静かな朝に、反省している今です。
2014年04月02日
社会の縮図か
というタイプではないので、
2冊 ・ 3冊並行して読んだりします。
似た設定の小説だったりすると
大変なこともあるけど ・ ・ ・ 。
もちろん、同じペースで進行するわけではありません。

伊勢神宮という1つのテーマで600ページを超していて、
結構なボリュームがあるので、
これ1冊を読む間に他のを6冊くらい読みました。
学者の世界でさえ、
( その世界に詳しい人は
「 学者の世界だからこそ 」 と言うかも知れないけど。 )
時の政治や、
世間の空気、
費用を出す人がどうすれば喜ぶか、
というような、
真実とは無関係な理由で
発表する内容が変化するんですね。
今では、伊勢神宮を見れば
誰でも立派な建物だと感じるけど、
そう思うようになったのは明治に
ドイツ人の有名な建築家が褒めたからで、
それまでは “ 簡素過ぎてみすぼらしい ”
と思われていたのだそうです。
( 諸々ほかの理由もあるけど ) 今、
私たちが伊勢神宮を見て立派だと感じるのは、
“ 常識人はそう感じなければいけない ” と、
誰かに思わされているのかも知れません。
さらには、
よく見かける、古代の建物の復元がありますが、
学者の世界では正しくないと解っていても、
お金を出す地元自治体が希望する、
見栄えがして人がよべる形にされることが多いとか。
この世の中がそんな仕組みで動いているのなら、
利益を目的にする企業が、
使う人のためにもならない自社の商品を売るために
適当にブームを作ったり、
政治を動かしたりするのは仕方ないのか、
などと考えてしまいました。