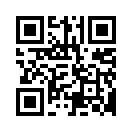2012年07月24日
なんかモヤモヤ ・ ・ ・
ヒトの頭は良く出来ていて、
目で見たものを脳ミソが色々と補正、加工してしまうんですね。
浄瑠璃を観ると非常に良く解りますが、
肉眼では黒子が消えてしまいます。
ところが、カメラのレンズを通すと
人形と黒子は同じ存在感になってしまう。
( 以前も書きました。 )
建物の完成写真を撮るとき、必ず悩むのが、
目で見た通りにはカメラが再現してくれないことです。
だから、実際とは違うけど
空間の “ 印象 ” が
同じになるように加工してもらうんですけど、
なんだか気分的にスッキリしない!
目で見たものを脳ミソが色々と補正、加工してしまうんですね。
浄瑠璃を観ると非常に良く解りますが、
肉眼では黒子が消えてしまいます。
ところが、カメラのレンズを通すと
人形と黒子は同じ存在感になってしまう。
( 以前も書きました。 )
建物の完成写真を撮るとき、必ず悩むのが、
目で見た通りにはカメラが再現してくれないことです。
だから、実際とは違うけど
空間の “ 印象 ” が
同じになるように加工してもらうんですけど、
なんだか気分的にスッキリしない!
2012年07月24日
学ぶ→崩す!
辻本好美さんの尺八演奏で、
背中を屈めて、片足上げるときがあるんですね。
そのことが気になって注目していると、
尺八の先の穴を膝でふさいでることに気付きました。
ご本人に訊いてみると、
高い音 ( だったかな? ) を出すための工夫だとか!
「 そんなに自由なものなんやぁ! 」
と思いました。
物語を書くとして、
結論 ( ラストシーン ) を書かない
なぁんて手法があると思わないじゃないですか。
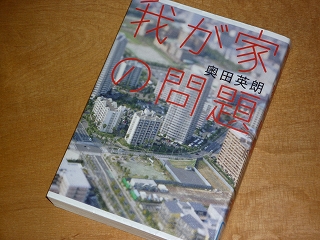
うちの奥さんが図書館で借りていたのを
横取りして読みました。
“ 生き方を考えさせる ” みたいな短編なのですが、
どの話も結論がありません。
花嫁を奪って2人で逃げるんだけれども、
ラストシーンがバスの遠ざかって行く後ろ姿で、
「 この先2人にどんなことが待っているか、
そちらで考えて下さい! 」
っていうような終わり方をする映画みたいな ・ ・ ・ 。
“ 型 ” っていうのは何にでもあるんでしょうけど、
基本を知った後は、
それを崩して自由に表現していくことで幅が広がる。
そんなことを
今強く考えています。
背中を屈めて、片足上げるときがあるんですね。
そのことが気になって注目していると、
尺八の先の穴を膝でふさいでることに気付きました。
ご本人に訊いてみると、
高い音 ( だったかな? ) を出すための工夫だとか!
「 そんなに自由なものなんやぁ! 」
と思いました。
物語を書くとして、
結論 ( ラストシーン ) を書かない
なぁんて手法があると思わないじゃないですか。
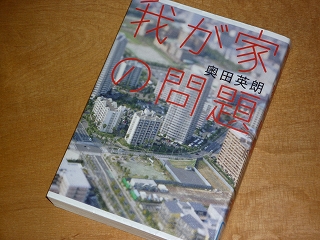
うちの奥さんが図書館で借りていたのを
横取りして読みました。
“ 生き方を考えさせる ” みたいな短編なのですが、
どの話も結論がありません。
花嫁を奪って2人で逃げるんだけれども、
ラストシーンがバスの遠ざかって行く後ろ姿で、
「 この先2人にどんなことが待っているか、
そちらで考えて下さい! 」
っていうような終わり方をする映画みたいな ・ ・ ・ 。
“ 型 ” っていうのは何にでもあるんでしょうけど、
基本を知った後は、
それを崩して自由に表現していくことで幅が広がる。
そんなことを
今強く考えています。