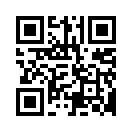2013年10月14日
けっこうなお点前で
面白いスタイルですね。
「 ご自分で点ててどうぞ! 」 っていう感じでした。

生駒市高山
日本の茶筅はほとんどがここで作られているのだそうです。

室町時代に鷹山城主の次男が初めて茶筅を作ったのが
( 考案したらしい ) この土地での茶筅づくりの始まりらしいので、
歴史はながいですね。
どんなところか見てみたくて訪れました。
中心になっている施設が 『 高山竹林園 』 のようです。

この近くには、茶筅の製造販売をされているところが
何軒もあるようでしたが、
ちょと気おくれしてそちらには行けませんでした。
この 『 高山竹林園 』 の中の茶室でいただいたのが
最初の写真の薄茶でした。
自分で点てて飲むっていうスタイルで、
お茶碗に抹茶が入っていて
ポットでお湯が出てくるっていうのは初めてです。
少々傷みの目立つ茶筅でしたが
茶道家として ( ウソッ! ) きれいに点てられたと思います。
美味しいお茶でした。
竹林も
少しずつですが、
竹の種類が沢山あってとてもきれいで、
ゆっくりと過ごせる空間でした。

「 ご自分で点ててどうぞ! 」 っていう感じでした。

生駒市高山
日本の茶筅はほとんどがここで作られているのだそうです。

室町時代に鷹山城主の次男が初めて茶筅を作ったのが
( 考案したらしい ) この土地での茶筅づくりの始まりらしいので、
歴史はながいですね。
どんなところか見てみたくて訪れました。
中心になっている施設が 『 高山竹林園 』 のようです。

この近くには、茶筅の製造販売をされているところが
何軒もあるようでしたが、
ちょと気おくれしてそちらには行けませんでした。
この 『 高山竹林園 』 の中の茶室でいただいたのが
最初の写真の薄茶でした。
自分で点てて飲むっていうスタイルで、
お茶碗に抹茶が入っていて
ポットでお湯が出てくるっていうのは初めてです。
少々傷みの目立つ茶筅でしたが
茶道家として ( ウソッ! ) きれいに点てられたと思います。
美味しいお茶でした。
竹林も
少しずつですが、
竹の種類が沢山あってとてもきれいで、
ゆっくりと過ごせる空間でした。

2013年10月14日
味わい ・ 深み
余分な部分を削ぎ落として、削ぎ落として、
研いて、磨いて最後に残ったものが
最高に美しくて、素晴らしいモノだと思うのですが、
最高に “ 魅力的 ” なモノかというと、
そうとも言い切れないような気がしています。
黒田街子パッチワークキルト展
での邦楽コンサートで、
塩高和之さんの琵琶と
田中黎山さんの尺八の演奏を聴きました。

ピアノなど、西洋の楽器の演奏では
楽譜にない音は雑音ですが、
邦楽の楽器の場合は、
尺八の息をはく風の音も
弦楽器で他の弦が共鳴してしまったり
ばちがたたいてしまったりする音も、
それは自然なモノとして音楽の中の
1つの要素になってしまうのだそうです。
夜の打ち上げで

塩高さんから伺ったところでは、
曲をつくるときには同じように
削ぎ落として、磨いて残った部分を取り出すのだけれど、
演奏のときには別の音も入って魅力的になるとか。
( 少し違ったかも知れませんが、
そんな意味のことを言われたと思います。 )
この感じは、
建築にも言えるのだろうと思います。
“ 味わい ” と言い換えても良いのでしょうか?
深みのあるモノづくり
は、そういうものなのだろうと思います。
研いて、磨いて最後に残ったものが
最高に美しくて、素晴らしいモノだと思うのですが、
最高に “ 魅力的 ” なモノかというと、
そうとも言い切れないような気がしています。
黒田街子パッチワークキルト展
での邦楽コンサートで、
塩高和之さんの琵琶と
田中黎山さんの尺八の演奏を聴きました。

ピアノなど、西洋の楽器の演奏では
楽譜にない音は雑音ですが、
邦楽の楽器の場合は、
尺八の息をはく風の音も
弦楽器で他の弦が共鳴してしまったり
ばちがたたいてしまったりする音も、
それは自然なモノとして音楽の中の
1つの要素になってしまうのだそうです。
夜の打ち上げで

塩高さんから伺ったところでは、
曲をつくるときには同じように
削ぎ落として、磨いて残った部分を取り出すのだけれど、
演奏のときには別の音も入って魅力的になるとか。
( 少し違ったかも知れませんが、
そんな意味のことを言われたと思います。 )
この感じは、
建築にも言えるのだろうと思います。
“ 味わい ” と言い換えても良いのでしょうか?
深みのあるモノづくり
は、そういうものなのだろうと思います。