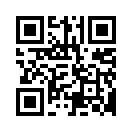2015年10月04日
作り話でもこんなことは ・ ・ ・
女の子に生まれたら、
みんな “ お姫様 ” とか “ お嬢様 ” とかに憧れるんでしょう?
きっと!
中には違う人もいるかも知れませんが、
私だって、お坊ちゃまに生まれたかったですモン ・ ・ ・ 。
お姫様で
お嬢様に生まれても、
生涯楽しいことばかりで幸せに過ごせるとは限らないようで、
“ いいところ ” に生まれたばかりに
大変な人生をおくった人の自叙伝です。

先月見学させていただいた広川町の東濱口家のお嬢さん
尚子さんが
元公家正親町三条家の嵯峨家へお嫁に行ったんですね。
( 明治時代のことです )
そして生まれた 浩 さんという女性が、
ラストエンペラー 愛新覚羅溥儀の弟 溥傑 と結婚しました。
軍が仕組んだ政略結婚です。
ここまでは、見学させていただいたときにお聞きした話で、
家系図ではこうなります。
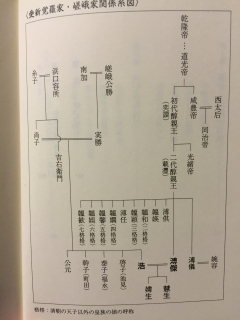
左上の方が濱口家で、
一番右の上の方に西太后の名前もあります。
当時の皇族や公家の家系では、
女の子を親戚にあずけて育ててもらうことが普通にあったようで、
浩 さんも母の実家濱口家で育ったらしいです。
愛新覚羅と結婚しただけでも、
戦中戦後、大変なことがあっただろうと想像できますが、
それだけではないんですね。
戦後、ようやく落ち着いてからでも
普通の人が経験しない大変なことが起こります。
ここではワザと書かないけど、
「 作り話でもこうはいかない! 」
っていうくらいの人生ですね。
先日、見学させていただいたお礼に改めて伺ったときに、
たまたま千葉から戻られていた
濱口家の当代ご当主にご紹介いただいて、
ご挨拶させていただこともあって、
ちょっと身近に感じる割には
そのスケールの大きさに感動しています。
( ちょっと違うけど他の言葉が浮かばない ・ ・ ・ )
みんな “ お姫様 ” とか “ お嬢様 ” とかに憧れるんでしょう?
きっと!
中には違う人もいるかも知れませんが、
私だって、お坊ちゃまに生まれたかったですモン ・ ・ ・ 。
お姫様で
お嬢様に生まれても、
生涯楽しいことばかりで幸せに過ごせるとは限らないようで、
“ いいところ ” に生まれたばかりに
大変な人生をおくった人の自叙伝です。

先月見学させていただいた広川町の東濱口家のお嬢さん
尚子さんが
元公家正親町三条家の嵯峨家へお嫁に行ったんですね。
( 明治時代のことです )
そして生まれた 浩 さんという女性が、
ラストエンペラー 愛新覚羅溥儀の弟 溥傑 と結婚しました。
軍が仕組んだ政略結婚です。
ここまでは、見学させていただいたときにお聞きした話で、
家系図ではこうなります。
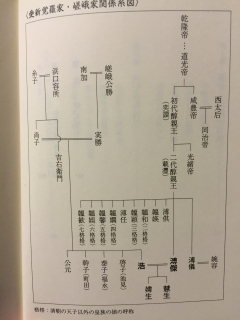
左上の方が濱口家で、
一番右の上の方に西太后の名前もあります。
当時の皇族や公家の家系では、
女の子を親戚にあずけて育ててもらうことが普通にあったようで、
浩 さんも母の実家濱口家で育ったらしいです。
愛新覚羅と結婚しただけでも、
戦中戦後、大変なことがあっただろうと想像できますが、
それだけではないんですね。
戦後、ようやく落ち着いてからでも
普通の人が経験しない大変なことが起こります。
ここではワザと書かないけど、
「 作り話でもこうはいかない! 」
っていうくらいの人生ですね。
先日、見学させていただいたお礼に改めて伺ったときに、
たまたま千葉から戻られていた
濱口家の当代ご当主にご紹介いただいて、
ご挨拶させていただこともあって、
ちょっと身近に感じる割には
そのスケールの大きさに感動しています。
( ちょっと違うけど他の言葉が浮かばない ・ ・ ・ )
2015年10月04日
四つ足が喰いてぇ!
って、
山を下りるなりオッサン3人で串カツ屋に直行なんてのは、
俗ですなぁ ・ ・ ・ 。
建築士会の近畿建築祭。

今年は和歌山県が登板に当たっていて、
昨日10月3日、高野山大学をメイン会場に
高野山一帯で開催されました。
高野山大学で歴史・民族を研究されている
森本准教授の基調講演
『 高野文化圏における歴史・民族 』 の中で、

御田祭りが取り上げられましたが、
いくつかの地域に残っているこの祭りの内、
完全に途絶えた後、
現代高校生たちによって復元されたのがあるそうで、
台本が残っているけど、
表現の仕方が解っていないものだそうです。
歴史や風俗を研究する人からは評価されない
この御田祭りが興味深いとのことです。
原型を守りながら受け継がれている
他の地域を複数研究することで、
途絶えて解らなくなっている地域の祭りがどんなものだったかを
推測することができる。
興味深い研究でした。
元は1つから起こっているはずなので、
少しずつ変化して今も残っている
御田祭りの原型を知ることができそうです。
こんな機会でなければ見ることが難しい建物もあります。
武田五一の設計により昭和4年完成の高野山大学図書館。

当時は “ 東洋一 ” と称されたそうで、
歴史の重みを感じることができる立派なものでした。

沢山勉強して、
1台のクルマで一緒に行った3人組が山から下りてきた時
「 昼は精進料理の弁当だったし、四つ足が喰いてぇ! 」
って、
シッカリ俗世間にリセットしたのでした。
山を下りるなりオッサン3人で串カツ屋に直行なんてのは、
俗ですなぁ ・ ・ ・ 。
建築士会の近畿建築祭。

今年は和歌山県が登板に当たっていて、
昨日10月3日、高野山大学をメイン会場に
高野山一帯で開催されました。
高野山大学で歴史・民族を研究されている
森本准教授の基調講演
『 高野文化圏における歴史・民族 』 の中で、

御田祭りが取り上げられましたが、
いくつかの地域に残っているこの祭りの内、
完全に途絶えた後、
現代高校生たちによって復元されたのがあるそうで、
台本が残っているけど、
表現の仕方が解っていないものだそうです。
歴史や風俗を研究する人からは評価されない
この御田祭りが興味深いとのことです。
原型を守りながら受け継がれている
他の地域を複数研究することで、
途絶えて解らなくなっている地域の祭りがどんなものだったかを
推測することができる。
興味深い研究でした。
元は1つから起こっているはずなので、
少しずつ変化して今も残っている
御田祭りの原型を知ることができそうです。
こんな機会でなければ見ることが難しい建物もあります。
武田五一の設計により昭和4年完成の高野山大学図書館。

当時は “ 東洋一 ” と称されたそうで、
歴史の重みを感じることができる立派なものでした。

沢山勉強して、
1台のクルマで一緒に行った3人組が山から下りてきた時
「 昼は精進料理の弁当だったし、四つ足が喰いてぇ! 」
って、
シッカリ俗世間にリセットしたのでした。